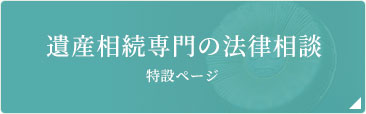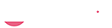弁護士法人Legal Homeは、大阪の豊中市に拠点を置き、法律問題にお悩みの方のお力になれるように日々尽力しております。
未成年者が相続人となる場合、成人だけが相続するケースとは異なる特別な注意が必要です。特に、親子が同時に相続人となる場合には「特別代理人」を選任する必要が生じることがあります。このブログでは、未成年者が相続人となった場合の遺産分割協議の進め方や、特別代理人の選任方法、借金がある場合の対処法などについてくわしく解説します。
成人年齢の定義
2022年4月1日以降、民法改正により、成年年齢が18歳に引き下げられたため、18歳未満が未成年者となります。
未成年者は遺産分割協議に参加できない
相続が発生した場合、相続人全員で遺産をどのように分割するかを話し合う「遺産分割協議」が必要となります。しかし、未成年者は法律上、この遺産分割協議に直接参加することができません。未成年者が相続人に含まれている場合、法定代理人がその代わりに協議に参加することになります。
通常、未成年者の法定代理人は親権者(親)であり、親が代理で協議を進めます。しかし、親権者も相続人となっている場合には、親自身が相続の当事者となり、子供と利益が対立するため、代理人を務めることができません。このような状態を「利益相反」と呼び、法律で親の代理行為が制限されるのです。
親権者が代理できない具体例
たとえば、父親が亡くなり、母親と子供が相続人となったケースを考えてみましょう。この場合、母親と子供がそれぞれ法定相続分として2分の1ずつを相続することになります。ここで問題となるのは、母親が遺産分割協議で自分の利益を優先し、子供の相続分を減らすような決定をする可能性があることです。このような事態を防ぐために、親が代理で子供の分を決定することは認められておらず、別途「特別代理人」を選任する必要が生じるのです。
特別代理人の必要性と役割
親が未成年者の代理人になれない場合、家庭裁判所に申立てを行い「特別代理人」を選任してもらう必要があります。特別代理人は、未成年者の利益を守るために、遺産分割協議に参加し、親子間の利害関係の対立を解消する重要な役割を果たします。
特別代理人は未成年者の権利を代弁し、遺産分割協議の内容が公正であり、未成年者の利益が守られるように進行します。この代理人には、親族や信頼できる第三者が選ばれることが多いですが、家庭裁判所で正式に選任されるまでは手続きを進めることができません。
特別代理人の選任手続き
特別代理人を選任するためには、未成年者が住んでいる地域を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。申立人は通常、未成年者の親権者や利害関係者(他の相続人など)が務めます。申立て後、家庭裁判所で審判がおこなわれ、適切な特別代理人が選任されます。費用としては、収入印紙や郵便切手などや、弁護士に依頼した場合には弁護士費用の準備が必要です。
申立てに必要な書類
・特別代理人選任申立書
・未成年者の戸籍謄本
・親権者または未成年後見人の戸籍謄本
・特別代理人候補者の住民票または戸籍の附票
・遺産分割協議書案
・利害関係を証明する資料(利害関係者が申立てをおこなう場合)
特別代理人なしで進めた遺産分割協議は無効に
親が未成年者の代理をすることができないにもかかわらず、特別代理人を選任せずに遺産分割協議を進めた場合、その協議は法的に無効となります。遺産分割協議書に親が勝手に署名・押印しても、法的には無効であり、不動産の相続登記や預貯金の払い戻しなどの手続きを進めることはできません。そのため、特別代理人を適切に選任し、手続きを進めることが非常に重要です。
未成年者が相続放棄する場合
未成年者が相続放棄をする場合にも、特別代理人が必要になることがあります。たとえば、親権者が借金を含めた遺産を相続し、未成年者には相続放棄させたい場合、子供と親の利益が対立するため、親が代わりに放棄の手続きをすることはできません。この場合も、家庭裁判所で特別代理人を選任する必要があります。
ただし、親も子も両方が相続放棄をする場合は、利益相反が発生しないため、特別代理人を選任せずに親が手続きを行うことが可能です。
遺産分割を遅らせるリスク
未成年者が相続人となった場合、特別代理人の選任や遺産分割協議が煩雑になることを理由に、子供が成人するまで遺産分割を待つことを考える方もいます。しかし、これはあまり得策ではありません。未成年者が相続人となった場合でも、適切な手続きを踏んで速やかに遺産分割を進めることが望ましいといえます。
遺産分割を遅らせることで、起こりうる問題
・相続財産の価値が変動する(特に不動産など)
・共同相続人間の関係が悪化する
・相続税の申告・納付が複雑になる
相続税の未成年者控除を活用
未成年者が相続人となった場合、「相続税の未成年者控除」を利用できることがあります。この控除は、相続人が20歳になるまでの年数に応じて、1年あたり10万円が相続税から控除されるというものです。
たとえば、10歳の未成年者が相続人となった場合、10年間分の100万円が控除されることになります。未成年者がいる場合には、この控除を最大限に活用することで、相続税の負担を軽減できる可能性があります。
未成年者が相続人となるケースでは、特別代理人の選任や複雑な手続きが必要
最後までお読みいただきありがとうございます。未成年者が相続人となるケースでは、特別代理人の選任や複雑な手続きが必要となりますが、適切な準備と手続きを行うことでスムーズに遺産分割を進めることができます。遺産を有効に活用するためにも、早めに特別代理人を選任し、問題が起こらないように対処することが大切です。複雑な手続きや法的な問題に直面した場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。弁護士法人Legal Homeでは、未成年者が関わる相続案件を含め、さまざまな相続問題に関する相談を承っております。ご不明な点やお悩みがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。