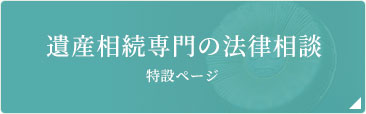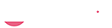弁護士法人Legal Homeは、大阪の豊中市に拠点を置き、法律問題にお悩みの方のお力になれるように日々尽力しております。相続に関する疑問や不安は、多くの方が抱えるものです。このページでは、相続に関してよく寄せられる質問とその回答をまとめています。複雑な相続の仕組みをわかりやすく解説し、皆様の不安解消のお手伝いをいたします。具体的な事例や法律の基本的な考え方も交えながら、相続や遺言に関する疑問にお答えしていきます。
相続に関するよくある質問
遺産相続でのトラブルにはどのようなものがありますか?
よくあるトラブルには以下のようなものがあります:
・認知症の遺言者による遺言書の出現
・相続人の一人による遺産の独占
・特定の相続人のみに相続させる遺言の出現
これらの問題に直面した場合は、弁護士と相談して対応を検討することが重要です。
相続手続きには期限がありますか?
はい、相続手続きには期限があります。主な期限は次の通りです。期限を守るため、スケジュールを作成し、計画的に手続きを進めることが重要です。
・相続税の申告と納付は相続開始から10カ月以内
・相続放棄は相続開始を知ってから3カ月以内
代襲相続とは何ですか?
代襲相続とは、相続人となるべき人が被相続人よりも先に死亡している場合に、その人の子(被相続人から見て孫)が代わりに相続することです。例えば、親が亡くなる前に子が死亡していても、その子に子供(孫)がいれば、孫が親の相続分を代わりに相続します。
遺留分とは何ですか?
遺留分とは、遺言書で指定された相続方法に関わらず、法定相続人に保証される最低限の遺産の取り分のことです。遺言書で特定の相続人に全財産を相続させるなど、法定相続人が遺産を相続できない場合でも、この遺留分は保証されます。
相続人がいない場合、遺産はどうなりますか?
相続人も特別縁故者もいない場合、遺産は国のものになります。相続人の有無が不明な場合は、家庭裁判所が選任した相続財産管理人が「官報」で相続人を探します。期間内に誰も申し出なければ、借金などを清算した後、残りの財産が国庫に帰属します。
相続手続で一番大変なことは何ですか?
相続手続きで最も大変なのは戸籍の収集です。相続人を確定するために、以下の戸籍謄本を漏れなく集める必要があります。
・相続人全員の現在の戸籍謄本
・故人(被相続人)が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本
これは、養子や認知した子供の存在を確認し、相続権を持つ全ての人を把握するために必要です。戸籍収集には時間と手間がかかりますが、銀行などでの相続手続きに必要なため、必ず取得しましょう。
相続放棄とはどのような手続ですか?
相続放棄は、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産(借金)も相続しない手続きです。
相続放棄の大切なポイント
期限…被相続人の死亡と借金の存在を知ってから3ヶ月以内
手続き場所…被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所
注意点…被相続人の財産を使用した場合、相続を承認したとみなされ、放棄できなくなる可能性があります
相続財産にはどのようなものが含まれますか?
相続財産には以下のようなものが含まれます。
現金、預貯金、株式、債券
不動産、借地権、借家権
自動車、貴金属、高価な美術骨董品
ゴルフ会員権
※死亡保険金(受取人が指定されている場合)や死亡退職金(会社の支給規定で受取人が指定されている場合)は、受取人の固有財産となり、相続財産には含まれません。
遺産分割はどれくらい時間がかかりますか?
遺産分割にかかる時間は、問題の複雑さによって大きく異なります。単純な分割の話し合いであれば、数ヶ月程度で終了することもあります。遺言無効の確認訴訟や遺産の確認訴訟など、裁判手続きが必要な場合は、かなりの時間がかかることがあります
寄与分とは何ですか?
寄与分とは、相続人が被相続人の生前に遺産の形成等に貢献した場合、他の相続人より多く遺産を受け取ることができる制度です。遺産の増大に寄与した部分を清算する趣旨から認められています。
遺言に関するよくある質問
遺言書が特に必要なのは、どんな人ですか?
誰でも遺言書は必要ですが、特に次のような場合は遺言の作成をおすすめします。
・法定相続以外の分け方を希望する場合
・子どものいない夫婦
・事実婚や内縁関係にある場合
・離婚や再婚で前配偶者の子供がいる場合
・隠し子がいる(可能性がある)場合
・遺贈や寄付を希望する場合
・財産が自宅のみで預金が少ない場合
・相続人が多い、または相続人同士の仲が悪い場合
・特定の子供に多額の援助をした場合や介護をしてもらった場合
遺言書があった場合、必ずその通りにしなければなりませんか?
相続人全員の同意があれば、遺言書の内容と異なる分け方をすることも可能です。遺産分割協議で全員が納得すれば、法定相続分にもとらわれず自由に分割できます。
遺言書が見つかった場合、まず何をすべきですか?
公正証書遺言以外の遺言書は、家庭裁判所での検認が必要です。特に、封をされた遺言書は勝手に開封せず、検認手続きの場で開封します。検認には相続人全員の戸籍謄本など、必要書類の準備が必要です。
遺言書の保管場所として適切なのはどこですか?
遺言書は相続人が気づかないと意味がありません。信頼できる人や専門家に預けて保管してもらうのが良いでしょう。法務局の遺言書保管制度の利用も検討できます。
自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらが良いのでしょうか?
保管の確実性や検認手続が不要である点から、一般的に公正証書遺言が望ましいとされています。ただし、状況に応じて適切な方法を選択することが重要です。
遺言書の検認とは何ですか?
検認とは、自筆証書遺言の場合に、遺言書の紙の種類やペンの種類などを裁判所が確認する手続きです。検認を経ないと不動産の登記手続き等ができません。ただし、公正証書遺言の場合、検認手続きは不要です。
封筒に入った遺言書を開封してしまいました。この遺言は有効ですか?
遺言書本体が法律の要求する要件を満たしていれば、開封しても遺言自体は有効です。ただし、開封した人は過料の制裁を受ける可能性があり、他の相続人から疑いをかけられる恐れもあります。
遺言執行者は遺言書に記載したほうが良いですか?
はい、遺言執行者を選任するのが望ましいです。遺言執行者がいないと、遺言の内容が実現できない可能性があります。信頼できる人や専門家を遺言執行者として指定することをお勧めします。
遺言や相続の問題で、信託銀行や司法書士、行政書士に相談しても大丈夫ですか?
それぞれの専門家には、得意分野や扱えることに違いがあります。それぞれの専門家に依頼をするメリット・デメリットを簡単にご紹介します。自分の状況を見極めて、適切な専門家に相談することが重要です。
| メリット | デメリット | |
| 信託銀行 | 実績が多く費用が明確 | 一定の条件下でしか扱えない場合がある |
| 司法書士 | 不動産登記にくわしい | 代理権に制限がある |
| 行政書士 | 行政手続きにくわしい | 紛争案件は扱えない |
| 税理士 | 税務に詳しい | 紛争案件は扱えない |
| 弁護士 | 紛争案件を含め幅広く対応 | 費用が事務所によって異なる |
遺言書の書き方で特に注意すべき点は何ですか?
自筆証書遺言の場合、以下の点に注意が必要です。
・全文を自筆で書くこと
・署名と押印を忘れずに
・作成日付を明記すること
・訂正がある場合は、訂正印を押し、加除字数を欄外に明記すること
※市販の遺言ノートに記入するだけでは、法的な遺言として認められない可能性があるので注意が必要です。