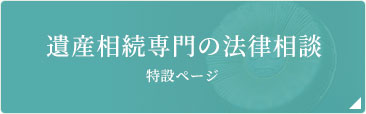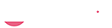弁護士法人Legal Homeは、大阪の豊中市に拠点を置き、法律問題にお悩みの方のお力になれるように日々尽力しております。相続において遺留分は相続人の最低限の権利を保護する重要な制度ですが、場合によってはこの権利を放棄することが有効な選択肢となります。遺留分放棄は相続トラブルを防ぎ、被相続人の意思をより尊重した相続を実現する手段として注目されています。しかし、その手続きや影響は複雑で、慎重な判断が必要です。このブログでは、遺留分放棄の意味から具体的な手続き、そしてメリットとデメリットまで、わかりやすく解説します。
遺留分放棄とは何か
そもそも遺留分とは?
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に認められる最低限の遺産取得割合です。例えば、会社経営者が遺言で後継者となる長男に遺産を集中させても、配偶者や子どもなどの相続人には遺留分が認められます。これらの遺留分権利者は、受遺者へ「遺留分侵害額請求」をすることで、遺留分に相当する金額の支払いを求めることができます。
遺留分の放棄とは
遺留分の放棄とは、遺留分権利者が遺留分の権利を自ら手放すことです。放棄すると、遺留分侵害額請求ができなくなり、不公平な遺言書によるトラブルを防ぐことができます。遺留分は、被相続人の生前でも死後でも放棄可能です。
相続放棄との違い
遺留分の放棄は相続放棄とは異なります。相続放棄は相続人としての地位を放棄し、資産も負債も一切相続しません。一方、遺留分放棄は遺留分のみを手放すため、相続権は失わず、残りの遺産取得や負債の相続は可能です。また、相続放棄は相続開始後3ヶ月以内のみ可能ですが、遺留分放棄は被相続人の生前でも可能です。
遺留分を放棄する手続き
被相続人が生きている間の方法
生前の遺留分放棄には、家庭裁判所の許可が必要です。被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所へ、遺留分権利者本人が申し立てます。必要書類には、家事審判申立書、不動産目録、財産目録、戸籍謄本などがあり、収入印紙800円分と連絡用郵便切手が必要です。
許可を得るために必要な条件
・遺留分権利者の自発的な意思であること
・正当な理由(例:長男への事業承継のため)があること
・放棄の代償(生前贈与など)があること
被相続人が亡くなった後の方法
死後の遺留分放棄は、遺留分権利者が侵害者へ「遺留分を請求しない」と意思表示すれば足ります。また、相続開始と遺留分を侵害する遺言・贈与を知ってから1年以内に請求しなければ、自然に権利が失われます。
遺留分放棄のメリットと注意ポイント
メリット
・相続トラブルの防止
・遺言通りの遺産分配が可能
・事業承継をスムーズに進められる
注意点
・基本的に撤回不可能
・生前放棄には代償が必要
・慎重な判断が必要
遺留分放棄は、相続トラブルを防ぎ、希望通りの相続を実現するための有効な手段
最後までお読みいただきありがとうございます。遺留分放棄は、相続トラブルを防ぎ、希望通りの相続を実現するための有効な手段です。ただし、代償の準備や相続人全員の納得など、慎重な判断と適切な手続きが必要です。十分な準備と話し合いをおこなった上で、遺留分放棄を検討しましょう。弁護士法人Legal Homeでは、遺留分放棄に関する詳細な相談を承っております。ご不明な点やお悩みがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。