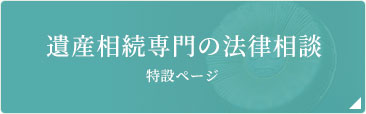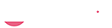弁護士法人Legal Homeは、大阪の豊中市に拠点を置き、法律問題にお悩みの方のお力になれるように日々尽力しております。遺産相続において、遺留分侵害額請求を受けることがあります。特に、被相続人の介護や財産管理を担当していた方は、使い込みを疑われるリスクがあります。このブログでは、遺留分侵害額請求の概要と、使い込み疑惑への対処法についてくわしく解説します。あわせて正当な支出を証明する方法や、トラブルを未然に防ぐための対策もご紹介します。
遺留分侵害額請求とは
遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)は、相続人が最低限相続できる遺産(遺留分)が侵害された場合に、その取り分の確保を請求することです。生前の贈与や遺言により、遺産の相続分が不当に減った際に行使されます。
例えば、被相続人に配偶者と2人の子供(長男と長女)がいて、「長男だけにすべての遺産を相続させる」という遺言を残して亡くなった場合、配偶者と長女は長男に対して遺留分侵害額請求をすることができます。
使い込み疑惑への対処法
被相続人の介護や財産管理を担当していた場合、他の相続人から使い込みを疑われるリスクがあります。このような事態に備え、以下の対策をしておくことが重要です。
客観的な資料の準備
使い込みではないことを証明するには、出金(使途不明金)について客観的な資料を用意することが必要です。具体的には以下のようなものが挙げられます。
・被相続人の医療費や介護記録
・不動産の管理費等の領収書
・業者との契約書
・生前贈与の場合は贈与契約書
事前の親族への相談と同意
親族等にあらかじめ相談をして同意を得ておくことも有効です。
具体的な対応
・被相続人の状況や必要な支出について、定期的に家族で話し合う機会を設ける
・預金の使用目的や範囲について、事前に親族間で合意を形成する
・重要な決定事項については、可能であれば親族の同意を書面で残しておく
記録の保管
領収書や契約書、介護記録などはすべて保管しておきましょう。これらの記録を日付順やカテゴリー別に整理し、必要な時にすぐに参照できるようにしておくことが大切です。
・被相続人の医療費や介護に関する領収書
・不動産の管理費等の領収書
・介護サービスや施設入所の契約書
・日々の介護内容や医療機関の受診記録
・生前贈与があった場合は、その贈与契約書
使い込み疑惑が生じた場合の対応
・客観的な証拠を提示して説明する
・被相続人のためにやむを得ない出金であった場合はその旨を説明する
・必要に応じて相続問題にくわしい弁護士に相談する
もしも遺産の使い込みが事実だった場合
仮に不当な使い込みであることが判明した場合、相手から返還を求めることになります。返還を求められた場合は、弁護士に依頼することも検討しましょう。ただし、依頼には費用が発生するため、経済的・心理的利益と費用をしっかり吟味する必要があります。
遺留分侵害額請求や使い込み疑惑に直面した場合、冷静な対応と適切な証拠の提示が重要
最後までお読みいただきありがとうございます。遺留分侵害額請求や使い込み疑惑に直面した場合、冷静な対応と適切な証拠の提示が重要です。事前の対策として、支出の記録を丁寧に残すことや、親族間での情報共有を心がけましょう。問題が複雑化した場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。弁護士法人Legal Homeでは、遺留分侵害額請求や遺産の使い込み疑惑に関する相談を承っております。ご不明な点やお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。経験豊富な弁護士が、あなたの状況に応じた最適な解決策をご提案いたします。